Amazonにおける本の紹介
アジャイル開発「最初の一歩」に好適!
ウォーターフォールとアジャイルは融合できる。
現場のリアルが詰まった、幸せな共存ストーリー。
過去アジャイルに挫折した人も、これなら大丈夫。【本書のポイント】
amazon.co.jp
・ストーリーでアジャイル開発の基本を学べる
・現場から目の前のことをどんどん解決していく方法が満載
・昔ながらの開発をしている会社でも、大企業でもできる
・開発に限らず、チームワークや部署間の連携にも効く
感想
ウォーターフォールベースのプロジェクトの中に、アジャイルを取り入れて「カイゼン」サイクルを回していくための実践方法が書かれた本です。
この本の面白いところは、小説パートの後に解説パートがあるところで、このおかげで実践の仕方がわかりやすくなっています。運用チームのリーダーとして配属された主人公が、無力感でいっぱいの組織をカイゼンするためにアジャイルを取り入れていく…というストーリです。
小説の内容自体は、展開がうまくいきすぎな感じもしますし、2020年に出版された本なので、ちょっと組織のイメージが古い感じはします。コロナをきっかけにチャットツールを導入した会社も多いでしょうし、バックログでタスクを管理するのもいまや当たり前ですよね。
この本を読んでいて、なるほど!と思ったのは、
「重要なのはアジャイルをする(Do Agile)のではなく、アジャイルになる(Be Agile)ことです。つまりアジャイルとは「あり方」なのです」
というところです。そもそも「アジャイル (Agile)」という単語は「素早い」「機敏な」という意味で、「変化に対して素早く対応すること」というのがアジャイルの肝なんですね。そう思うと、方法論にとらわれるのではなくて、現場の問題に柔軟に対応していくというのが「アジャイルになる」ということなのですね。
そういう意味では、タイトルで示唆されているように、「ウォーターフォール型の開発とアジャイルは共存できる」というのは確かにその通りで、ウォーターフォールのやり方に「アジャイルになる(変化に対して柔軟になる)」ことをとりいれるのは全く無理でも不自然でもないことなんだなあと理解できました。
もちろんこの本ではアジャイルのプラクティスの実践例・適用例が載っているので、それを参考に実践することで、アジャイルな組織になっていくと思います。
とくに本書で紹介されている「全メンバーの意見を聞く(付箋に書き出してもらって一斉に発表してもらうとよい)」「新しい方法を取り入れるときは、失敗を恐れずお試ししてみる」というのは自分の組織にも取り入れることができそうです。
以前書評を書いた『世界一流エンジニアの思考法』では、「日本の組織は失敗を恐れすぎている。それが日本のよくないところ。」と書かれていて、たしかにそうだよなあと思ったのでした。(書評ブログはこちらhttps://datascience-beginner.mofumofu.page/?p=552)失敗してもいいから、スモールステップで試してみる、ダメならすぐにやめればいいだけ、というアジャイルな考え方があたりまえになれば、もっとクリエイティブになっていくんじゃないでしょうか。
小説パート+解説というスタイルなので、とても読みやすいですし、「アジャイルっていうけどうまくいかないんだよね…」と思っている人は読んでみるとアジャイルに対する理解が深まると思います。おすすめ!
概要
第1章 無力感
ITシステム開発における問題点として、開発メンバーと顧客の間で要件が決定され、運用チームの声が無視される傾向にあります。運用チームはユーザーテスト工程から参加するものの、その意見が開発に反映されない状況が多いです。アジャイル開発の導入は、この問題に対応するための解決策として提示され、個人との対話、動くソフトウェア、顧客との協調、変化への対応を重視しています。また、ウォーターフォール方式とアジャイル方式は互いに補完しあう関係にあると解説しています。
第2章 小さな一歩
チーム内でインシデントに対する対応が一貫性を欠き、情報共有が不十分である問題を指摘しています。この根本原因としてチームとしての機能不全が挙げられており、個々に作業を進める体制が問題を引き起こしていると分析しています。解決策として、チケット管理システムの活用や、定期的な情報共有の場を設けることで、インシデントの透明性を高め、チーム全体の対応力を強化する方法が提案されています。
第3章 抵抗
タスク管理の方法に関して、新規チケットの評価や未クローズチケットの進捗確認の重要性を強調しています。また、ふせんを使用してタスクを視覚化し、進行状況を管理する手法を提案しています。組織変革の推進には、メンバーが変化を受け入れ、積極的に取り組む姿勢が必要であると述べており、試行錯誤を重ねながら徐々に改善を図ることの重要性を説いています。
第4章 変化
「井戸端型意思決定」の問題点を指摘し、情報共有と意思決定プロセスの改善の必要性について言及しています。チーム横断でのタスク管理の導入によるメリットとして、進捗管理の容易化と組織全体の記憶装置としての機能が挙げられています。タスク名を作業ベースで統一し、タスクの状態を「説明」項目に明記することで、効率的なタスク管理を実現する方法が提案されています。
第5章 意外な理解者
アナログとデジタルのツールを効果的に組み合わせることの重要性を強調しています。問題解決のために可視化の手法を導入することが提案されており、リーダーシップスタイルの変化として、問題解決をチーム全体で共有し取り組むサーバント型リーダーシップの重要性が強調されています。
第6章 相手のキーワードに飛び込む
メールコミュニケーションの限界として、誤送信や時間がかかる問題を指摘し、チャットツール導入の効果を強調しています。コミュニケーションの質向上のためには、相手の関心事に注意を払い、共通の目標を見出すことが重要であると述べています。
第7章 快感体験
組織内のコラボレーション促進を目指し、「おやつ神社」の導入など、カジュアルなコミュニケーションの場の設置が推奨されています。このような取り組みによって、チーム間の交流が促進され、組織内でのポジティブな関係が育成されることが強調されています。
第8章 衝突からのセイチョウ実感
チーム力向上に向けた具体的な手法として、ドラッカー風エクササイズやKPTのふりかえり、BacklogとSlackの活用が提案されています。また、チーム内での4つの重要な質問と、ふりかえりのプラクティスの重要性が強調され、チームの成長と成果向上に必要な要素が詳述されています。
第9章 越境
負の連鎖を断ち切るためにサーバント・リーダーシップの導入が提案されており、感謝の表現や他者への配慮がチームの成長に不可欠であると強調されています。また、クロスファンクショナルな組織構造の重要性とアジャイルな組織の価値観が説明されています。
第10章 さらなるセイチョウ
エンゲージメント向上のためには、「人」、「場」、「ツール」、「プラクティス」、「仕掛け」、「マインドづくり」などの複合的な実施が必要であると説明しています。小さな成功事例から始め、広げていくことの重要性、セイチョウのための仕掛け、ナレッジマネジメント、発信文化の推進、テスト駆動開発とSpecification By Exampleの重要性が強調されています。
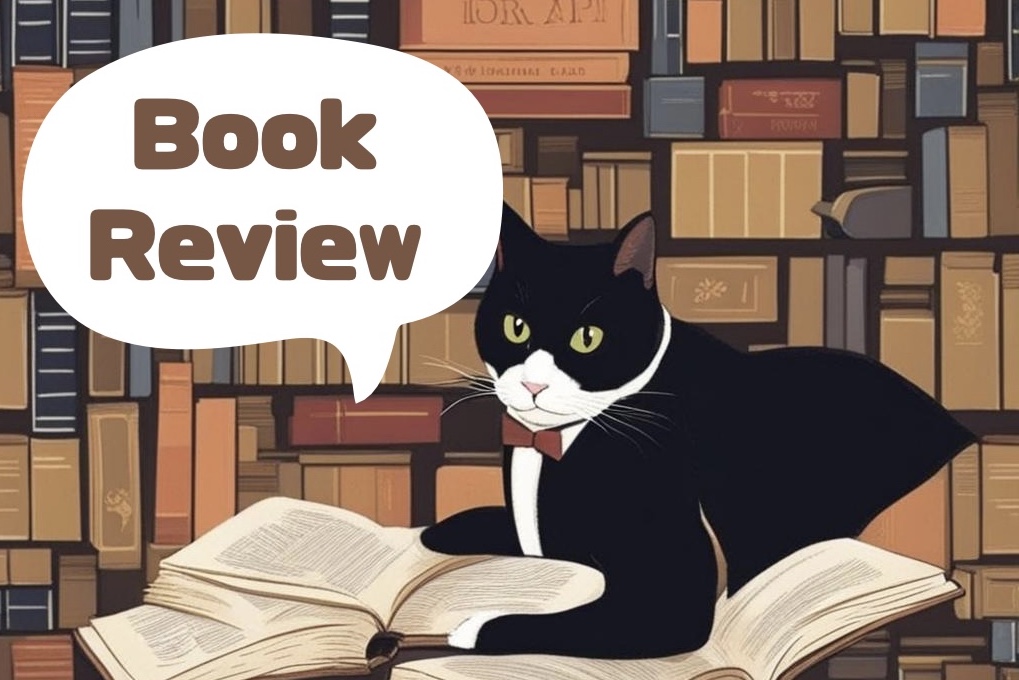

コメント